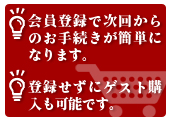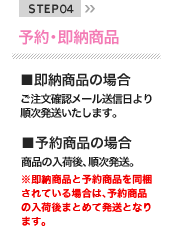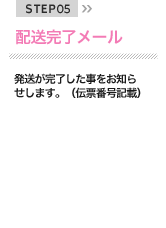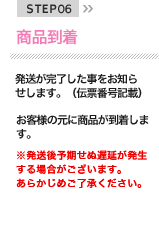五月人形とは
 端午の節句について
端午の節句について端午の節句は、奈良時代から行われている古い行事です。
端午とは五月の初めの午(うま)の日のことで、現在ではこどもの日となっていますが、本来は端午(たんご)の節句といい、災厄を避けるための行事が行われる重要な日でした。宮廷ではこの日に菖蒲(しょうぶ)やよもぎを冠に飾ったり柱に下げ、また災いをもたらす悪鬼を退治する騎射(うまゆみ)や競馬(くらべうま)などの勇壮な催しも行われていました。
その後、端午の節句は武家のみならず民間にまで広がって、男の子の誕生を祝う日となりました。端午は、奇数が重なることをおめでたいとする考え方から、やがて五月五日に定着しました。
男の子が生まれて初めて迎える五月五日のお節句を、初節句といいます。
五月人形について
古来、天の神様を招くため戸外に立てた武具やのぼり旗は、江戸中期には内飾りにも作られ、兜の飾りに取り付けられていた人形が五月人形になっていきました。
ことに武家社会では端午を象徴する菖蒲(しょうぶ)が、武道・武勇を重んじることを意味する「尚武」と同じ音であることから、五月人形は男の子が多くの困難に打ち勝ってたくましく成長していくことを願うための大切な飾りとなりました。身を守るための鎧兜(よろいかぶと)を飾る風習は、お子さんの健やかな成長を願う両親や家族の暖かな祈りが込められています。
五月人形と鯉のぼり
端午の節句の飾りには、内飾りと外飾りがあります。
鎧・兜飾りや子供大将飾りが内飾り、鯉のぼりや武者絵のぼりが外飾りです。成長を祈る内飾りと出世を願う鯉のぼりの両方を飾るのが望ましいかたちとされていますが、地方によりどちらをメインにするかは若干異なりますので、その土地の風習に合わせてご家庭にふさわしい飾り方をしてください。
五月人形は誰が買うのでしょうか
おひな様の場合は、嫁いだ娘と孫に会いに行くために、母方がおひな様を買って会いに行くことから始まったようです。
五月人形の場合も同様ですが、五月人形を母方、鯉のぼりを父方というように分けてご用意される場合が多いようです
鯉のぼりについて
 男の子が生まれて、初めて迎えるお節句(五月五日)を初節句といい、生まれたばかりの赤ちゃんが、丈夫にたくましく成長するよう、願いを込めてお祝いをする行事です。
男の子が生まれて、初めて迎えるお節句(五月五日)を初節句といい、生まれたばかりの赤ちゃんが、丈夫にたくましく成長するよう、願いを込めてお祝いをする行事です。鯉のぼりは、江戸時代に町人階層から生まれた飾りです。鯉は、清流はもちろん池や沼でも生息することができる生命力の強い魚です。
その鯉が急流をさかのぼり、竜門という滝を登ると竜になって天に登るという中国の伝統にちなみ(登竜門という言葉の由来)子供がどんな環境にも耐え、立派な人になるようにとの立身出世を願う飾りです。
商品説明
鯉のぼりは1.2mセットからございます。(種類によっては1.5mセットからとなります。)
鯉のぼりの生地は、基本的にポリエステルとナイロンの2種類があり、ポリエステルの方が雨や汚れに強く、色あせもしにくい生地となっております。また、撥水加工を施した生地もございます。
店内に飾っていますので、実際に触ってご確認いただけます。⇒ネット販売では不要でしょう。
2.0mセット(吹き流し2.0m、真鯉(黒)2.0m、緋鯉(赤)1.5m、小鯉(青)1.2m、矢車、ポール、ロープ、スタンド、水袋)
1.5mセット(吹き流し1.5m、真鯉(黒)1.5m、緋鯉(赤)1.2m、小鯉(青)1.0m、矢車、ポール、ロープ、スタンド、水袋)
1.2mセット(吹き流し1.2m、真鯉(黒)1.2m、緋鯉(赤)1.0m、小鯉(青)0.8m、矢車、ポール、ロープ、スタンド、水袋)
・3m~10mの大きなものもございます。⇒お問い合わせください。
・小鯉も各種ございます。(1~2日でお取り寄せができます。)⇒お問い合わせください。
・吹き流しに家紋や名前入れも承ります。(日数がかかりますので、お早めにお願い致します。)