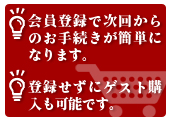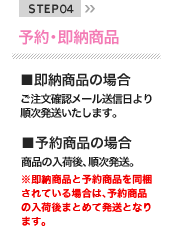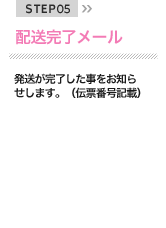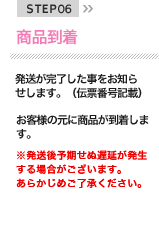ひな人形とは
 ひな人形のひな(雛)とは、鳥の雛のように小さいという意味で、生まれたばかりの鳥の子がヒヒと鳴くことから、古くは「ひいな」と言われていました。
ひな人形のひな(雛)とは、鳥の雛のように小さいという意味で、生まれたばかりの鳥の子がヒヒと鳴くことから、古くは「ひいな」と言われていました。もともとは平安時代に十文字に作った棒の上に布でくるんだ顔をつけただけのもので、小児のお祓(はら)いに用いられていました。
そこから人形の形になっていき、お子様が無事に健康に育つように、という願いが込められたお守りとなりました。
おひな様を飾る時期
 ひな祭りは、3月3日の桃の節句です。
ひな祭りは、3月3日の桃の節句です。飾り始めるのは諸説ありますが、節分が終わった立春(2月4日)頃がよいでしょう。
雨水の日(2月19日)という説もありますが、これでは飾っている期間が少々短いのではないでしょうか。
おひな様を片付けるのは、3月3日が終わって啓蟄(けいちつ)(3月6日)ごろのお天気のよい日にしてください。
早く片付けないとお嫁にいけない!というのは嘘ですよ。
これは長く出しておくと季節が暑くなり湿気が出てくるので、早めに片付けましょう。
片づけができないようでは、誰もお嫁にもらってくれないよ、と親が子供と一緒に片づける時によく言われたところからきているようです。
人形の供養
上で記しましたようにひな人形は、個人のお守りですから親から子へと引き継ぐものではありません。お役目を果たされたおひな様は、いつまでも置いておかずに供養してあげましょう。供養のタイミングは、成人したときや結婚したとき、引越しをするときなどでよいでしょう。
また、赤ちゃんが生まれてその子の新しいおひな様を購入する時ならタイミング的にわかりやすいかもしれませんね。
供養については、お道具は処分し、供養するのはお人形だけです。お近くの神社にお問い合わせください。
人形の種類
十五人揃いのお人形をご紹介します。
1.親王 お内裏様とお雛様(二人で内裏雛ともいいます)
2.三人官女 向って右から長柄の銚子、三方、提子(ひさげ)を持った宮廷の女官。
3.五人囃子(ごにんばやし) 五人一組の囃子方で向って右から謡(うたい)、横笛、小鼓、大鼓、太鼓。
4.随身(ずいしん) 弓矢を持った二人一組で左大臣・右大臣ともいいます。
5.仕丁 三人一組で向って右から立傘・沓(くつ)台・台笠持ちの順に飾り、笑い、泣き、怒りの表情から三人上戸(じょうご)とも言われます。
ひな飾りの種類
 段飾り
段飾り七段飾り、五段飾り、三段飾りなどがあります。段数が多くなるとお人形やお道具も多くなり、段を組み立てて飾ります。大変豪華なお飾りができます。
 親王飾り
親王飾りお人形は親王二人だけで、お道具や桜橘、屏風を飾ります。大きさはいろいろで、人形師が製作したものは、着物が正絹であったり高価なものが多くあります。
 収納飾り
収納飾りお人形は、親王だけのものと三人官女もいる五人飾りものもがあり、飾り台にお人形やお道具を入れられるようになっていますので、コンパクトになります。
 ケース飾り
ケース飾りガラスケースやアクリルケースのものがあり、ケースの左右に柱が無いパノラマケース、左右に斜めに面がある六角ケースなどがあります。
お人形は、親王飾りから十五人飾りまであります。にぎやかな感じがお好みの方は、人数が多いほうがいいかもしれませんね。
 立雛(たちびな)
立雛(たちびな)ひな人形の初期の姿は立雛でした。現在では坐(すわり)雛(びな)が大半ですが、立雛にはいにしえの気品が感じられます。
衣裳着人形と木目込人形(いしょうぎにんぎょうときめこみにんぎょう)
 ひな人形には、通常よくある衣裳を着せ付けた衣裳着人形と桐塑(とうそ)や木で作られた人形の胴体部分に衣裳を貼り、きめこんだ丸いお顔が特徴の木目込人形があります。木目込人形もかわいいですよ。
ひな人形には、通常よくある衣裳を着せ付けた衣裳着人形と桐塑(とうそ)や木で作られた人形の胴体部分に衣裳を貼り、きめこんだ丸いお顔が特徴の木目込人形があります。木目込人形もかわいいですよ。